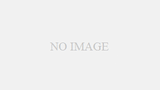「頑張って記事を書いているのに、なかなかアクセスが増えない…」
そんな悩みを抱えていませんか? 私も、数年前はまさに同じ壁にぶつかっていました。
最初の半年はPVも収益もゼロだった私ですが、「SEO構成案」を学んだことがきっかけで、今では月5万PV、安定して収益が出るようになりました。
この記事では、初心者でも無理なく実践できる「SEO構成案の作り方」と、その考え方を自然に取り入れる方法を、ストーリー形式でお伝えします。
なぜSEO構成案が必要なのか?
私がブログを始めた頃、とにかく思いついたことを好きなように書いていました。
でも、どれだけ一生懸命に書いても、検索順位は上がらず、読者の反応もほとんどゼロ…。それもそのはず。読者が「知りたいこと」と、私が「書きたいこと」がズレていたんです。
このズレを埋めるために必要なのが、SEO構成案。検索ユーザーの「知りたい」に寄り添いながら、効果的に情報を伝える設計図のようなものです。
初心者でもできるSEO構成案の作り方
では、実際にどうやってSEO構成案を作ればいいのでしょうか?
私が初めて取り組んだ方法を、5つのステップでご紹介します。
ステップ①:キーワードを決める
まずは「誰に何を伝えるか」を明確にしましょう。今回の記事なら、「SEO構成案 作り方 初心者」がキーワードです。
Google検索やキーワードツールを使って、関連するキーワードの検索ボリュームや競合性を調べておくと安心です。
ステップ②:検索意図を読み解く
検索ユーザーは、なぜそのキーワードで検索したのでしょう?
「SEO構成案 作り方 初心者」であれば、「ブログ初心者だけど、SEOに強い記事を書きたい」「具体的な手順が知りたい」といったニーズが想定されます。
これを理解するためには、実際にGoogleで検索して、上位10記事をざっと確認するのがおすすめ。「どんな疑問に答えているか」「どんな構成になっているか」をメモしておきましょう。
ステップ③:記事のゴールを決める
構成案を作るとき、まず「読者に最終的に何を持ち帰ってもらいたいか」を決めておくと、ブレにくくなります。
今回の記事のゴールは、「初心者でも自然にSEO構成案が作れるようになること」です。
ステップ④:見出しを設計する
読者が読み進めやすいように、記事全体の骨組みを設計します。たとえば:
- SEO構成案とは何か
- 初心者がつまずくポイント
- 5ステップでできるSEO構成案の作り方
- 実際のテンプレート例
- ツールを使って時短する方法
- まとめ・次のアクション
こうした見出しをあらかじめ決めておくことで、読者の関心を逃さずに、自然な流れで読み進めてもらえます。
ステップ⑤:想定読者を常に意識する
最後に大切なのは、「誰に向けた記事なのか」を常に意識すること。
専門用語が多すぎると初心者は離れてしまいますし、逆に表面的すぎても信頼されません。ちょうどよい言葉のレベルで、読者の視点に立った表現を心がけましょう。
実際にSEO構成案を活用してみたら…
私が初めてSEO構成案を使って書いた記事は、「副業ブログ 初心者 始め方」というテーマでした。
以前なら勢いだけで書いていた内容を、構成案に沿って
- 共感を得る導入
- 体験談と失敗事例
- 改善策と具体的ステップ
- まとめと次の一歩
という流れで仕上げたところ、なんと3週間後には検索1ページ目に表示されるように…!
「ああ、こういうことだったのか」と、初めてSEOの効果を体感した瞬間でした。
便利なツールも活用しよう
「自分で全部やるのは大変…」と思った方、大丈夫です。
今は構成案作成を支援してくれる便利なツールもたくさんあります。
たとえば:
- ラッコキーワード:関連キーワードの抽出に
- Googleキーワードプランナー:検索ボリュームの確認に
- AIライティングツール:構成案のたたき台に
ツールは「考える時間の短縮」に使い、軸となる構成や読者への想いは、自分でしっかりと設計する。これが理想的な使い方です。
まずは小さく始めてみよう
「SEO構成案」と聞くと難しそうに感じるかもしれません。でも、要は「読者にとって親切な記事」をつくるための準備にすぎません。
最初から完璧を目指さなくても大丈夫。まずは1記事だけ、「読者の検索意図に沿って」構成を考えてみてください。
書きやすくなるだけでなく、読んでもらえる実感も得られるはずです。
まとめ|あなたの記事は、もっと読まれる
SEO構成案は、初心者にこそ役立つ“地図”のような存在です。
キーワードをもとに検索意図を読み解き、読者の疑問を自然に解決する構成を作る。それだけで、ブログの成果は大きく変わります。
私自身、「自分の想いをちゃんと届けるには、読者の立場になることが何より大事」と実感しました。
あなたの記事は、まだまだ伸びしろだらけ。小さな一歩が、大きな成果につながります。
ぜひ、今日から「構成案づくり」始めてみてくださいね。